2025年3月18日
●アーカイブ動画(以下よりご視聴ください)
※動画のコピーやURLの転送はご遠慮ください。
●動画視聴された方へ:内容についてのご感想やご意見を以下のフォームよりお聞かせください。
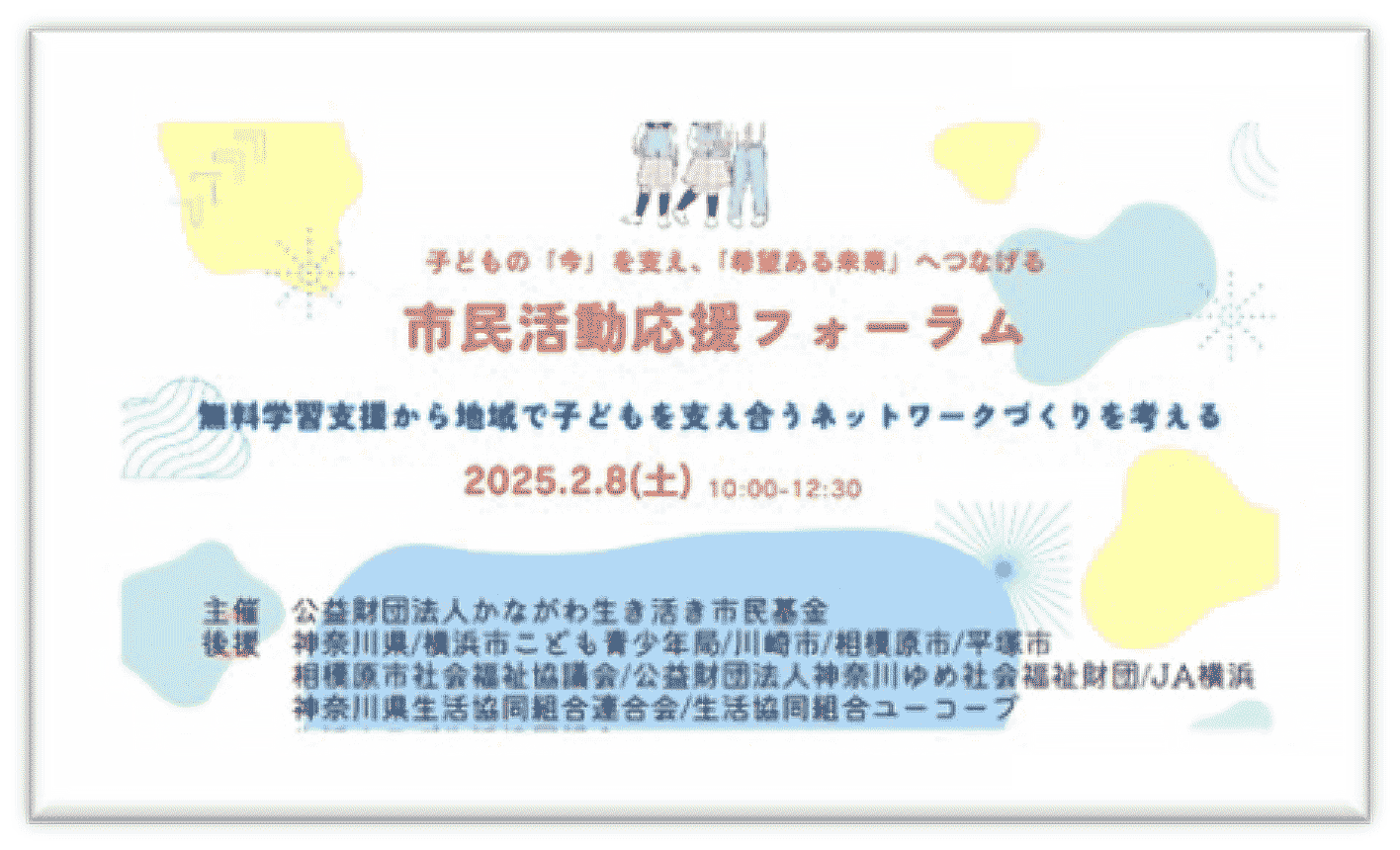
子どもの「今」を支え、「希望ある未来」へつなげる『市民活動応援フォーラム』
無料学習支援から地域で子どもを支え合うネットワークづくりを考える
日時 2025年2月8日(土)10-12:30
場所 オルタナティブ生活館 地下1階 @スペースオルタ
後援 神奈川県/横浜市こども青少年局/川崎市/相模原市/平塚市/相模原市社会福祉協議会/公益財団法人神奈川ゆめ社会福祉財団/JA横浜/神奈川県生活協同組合連合会/生活協同組合ユーコープ/生活クラブ生活協同組合
参加者 生活クラブ32人、生活クラブ運動グループ6人、市民活動団体14人、その他14人
今回のフォーラムは、「どんな境遇にあっても希望ある未来に向けて、子どもたちの「今」をつくる活動を支えあうネットワークのしくみを広げる」をテーマに開催しました。

・基調講演には、『無料塾の必要性と可能性』と題し、『教えているのは、希望。「無料塾という」という生き方』の著者で認定NPO八王子つばめ塾理事長の小宮位之氏をお迎えしました。経済的に苦しい家庭の子どもでも高校進学を諦めずにすむようにと「八王子つばめ塾」を始めて12年。理念は、ボランティア講師に支えられ進学し、夢をあきらめないことで「自分もいつか人の役に立つ人間になりたい」と考える人材を育てること、ツバメが巣立って、また同じ巣に戻って来るように、100%ボランティアで成り立っている「つばめ塾」から巣立った卒業生が、ボランティアというフィールドに戻ってくることであるといいます。こうしたつばめ塾のやり方を見学する人は後を絶たず、そのノウハウを惜しみなく伝授することで、各地で無料塾が広がってきています。
ご自身の子ども時代の貧困の経験も踏まえ、30年は継続するという強い意志が伝わるパワフルな語りに会場全体が引き込まれました。
・パネルディスカッションは、「無料学習支援を子どもを支え合うネットワークづくりをかん考える」をテーマにすすめました。
① メダカのお弁当 鈴木雄大氏
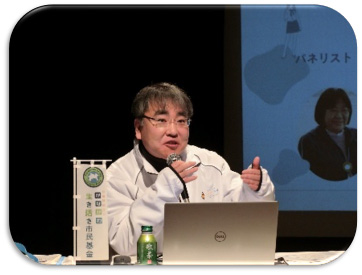
毎朝のお弁当配布を皮切りに、地域食堂、パントリー等を展開する食事食材支援事業と地域と連携した無料学習支援事業メダカの学校についての報告があり、今まで平日のみだったお弁当配布を、休日も必要としている人がいるということで、2025年4月から365日配布にチャレンジするとの決意表明がありました。
2023・2024さがみはら子どもの居場所サミットでは、地域、行政、他機関など多方面にアプローチし、相模原の未来を担うこどもたちのための一つのプラットホームのような存在を目指してきたが、2025年度は地域の活動団体と支援者をマッチングする「さがみはら子ども・子育て・ママ&パパ 支援大賞」を企画しているとの報告がありました。
② 子ども学習支援グループ須賀の寺子屋 大野文氏

本人や家庭の事情により学習等が困難なこどもや子育て家庭に学習支援や食支援を行い、将来の夢や希望を持って進学・就職できる青少年の健全な育成を活動の目的としているとのこと。
活動の始まりは、①学校へ通わせることのできない家庭②発達に問題を抱えていたことに気が付かない家庭の二人の小学生との出会いからで、学習支援、食支援、相談対応、支援員研修を行うことで子どもを包括支援しているとの報告がありました。現在は、小学生学習教室を毎月2回 地域の公民館で、中高生学習支援を毎月4回、太洋中学校体育館会議室で行い、企業・団体・学校・NPO等の協力と連携で運営しています。
③ みんなのいばしょ ポプケ 武田 恵氏

「ポプケ」とは、アイヌ語で「あたたかい」という意味。社会不安、経済格差等、子ども達がのびのびと不安なく育つことが難しい現代社会にあって、子ども達に社会のあたたかさを伝えたい、人のぬくもりを伝えたいとの思いから、ボランティアで運営する任意団体としてスタート。小中学生対象のいばしょ 週2回、個別学習支援 週1回、ほっと♪ポプケ(大人も子どももどなたでも)週1回、ポプケ文庫を開いているとのこと。
身近な地域での活動連携へのチャレンジとして、相模原市中央区こどもの居場所連絡協議会「今こどもたちのいるところ」を発足したとの報告がありました。

各団体の報告を受け、身近な地域にこどもを支援する活動が多様あり連携していくことの意義を確認しつつ、以下の点について議論を深めました。
・行政との連携をどう深めていくか。
→特に、行政との連携は難しい。小学校でチラシを配布してほしいとお願いしても、校長先生によって対応が全く違う。行政の各課も担当者間で引継ぎされることは少なく、人が変わるたびに苦労してきた。しかし、活動を継続したことで地域と利用者との信頼ができ実績を積んでいくことが一番の力となる。この『実績と信頼』で行政との連携を勝ち取ってきた。
→子どもの抱える問題点は個人情報保持の観点から簡単に共有はできないが、子ども本人、ご家族の了解を取ってから相談するようにしている。
・活動運営で困っていること。
→資金面は大きな課題であることは変わりないが、一番は人材の確保と高齢化が課題。直接声かけをしたり、社協等の市民ボランティア登録制度やマッチングなどの活用、ボランティア同士の口コミなどで広げているが、慢性的な課題である。
・この活動を始めた目的は何か。
武田氏 自分自身が住んでいたい社会をつくるため。子どもは未来の希望である。
大野氏 信じられる大人がいることを伝えたい。
鈴木氏 次世代への足跡を残す。どれだけ愛をこめられるか。
・まとめ
経済的に苦しい家庭の子どもの進学は厳しい状況である。生まれた家庭にお金があるかないで、子どもの人生の選択肢が決まってしまうという社会の現状を善しとせず、また、子どもが大人を信頼できる社会を目指して無料学習支援や食事・食材支援等を地域ですすめる小宮さん、鈴木さん、大野さん、武田さんにお集まり頂き、子どもの「今」を支え、「希望ある未来」へつなげる 市民活動応援フォーラムを開催した。参加者は地域で子ども支援活動をする団体、生活クラブ組合員が多くを占めた。
参加者のフィードバックには、何か自分ができることを考えたい。今自分がやっている活動が間違っていなかったとの確信をもてたとの意見もあった。これからの神奈川の活動に何かつながっていくことを期待したい。
最後に、「子どもの貧困に立ち向かう市民活動応援基金」への寄付参加を呼び掛けた。

このホームページに記載の記事 ・ 写真・イラストなどの無断転載を禁じます。
Copyright(C) 2017. かながわ生き活き市民基金 All rights reserved.